納屋は贈り物ではなかった。風化した木と朽ちかけた梁に包まれた最後の侮辱だった。兄たちが不動産や銀行口座のことで言い争う中、クレアは畑の端にひとり立ち、今自分が所有している垂れ下がった屋根を見つめていた。彼女の遺産?埃と静寂。
掃除していると言うと、兄たちは笑った。ガラクタを掘り出せば、何か光るものが見つかるかもしれない、と。ブライアンは、勧められてもいないワインで乾杯しようとした。サムはただ笑って、”自業自得だ “と言った。
彼女はお金のために残ったのではない。彼女は仕事も人生も投げ出し、面会にも行けない父親の面倒を見た。それでも、彼女には価値がない、ふさわしくないと思われていた。しかし、納屋には父親の思い出があった。そして彼女は立ち去らなかった。
クレア・ホイットモアは拍手はおろか、感謝の言葉も期待していなかった。しかし、幼い頃住んでいた家の砂利道に立ち、ポーチでウイスキーを飲みながら談笑する兄たちを眺めていると、見慣れた締め付けられるような痛みが胸に迫ってきた。その痛みは新しいものではなかった。ただ大きくなっただけだ。
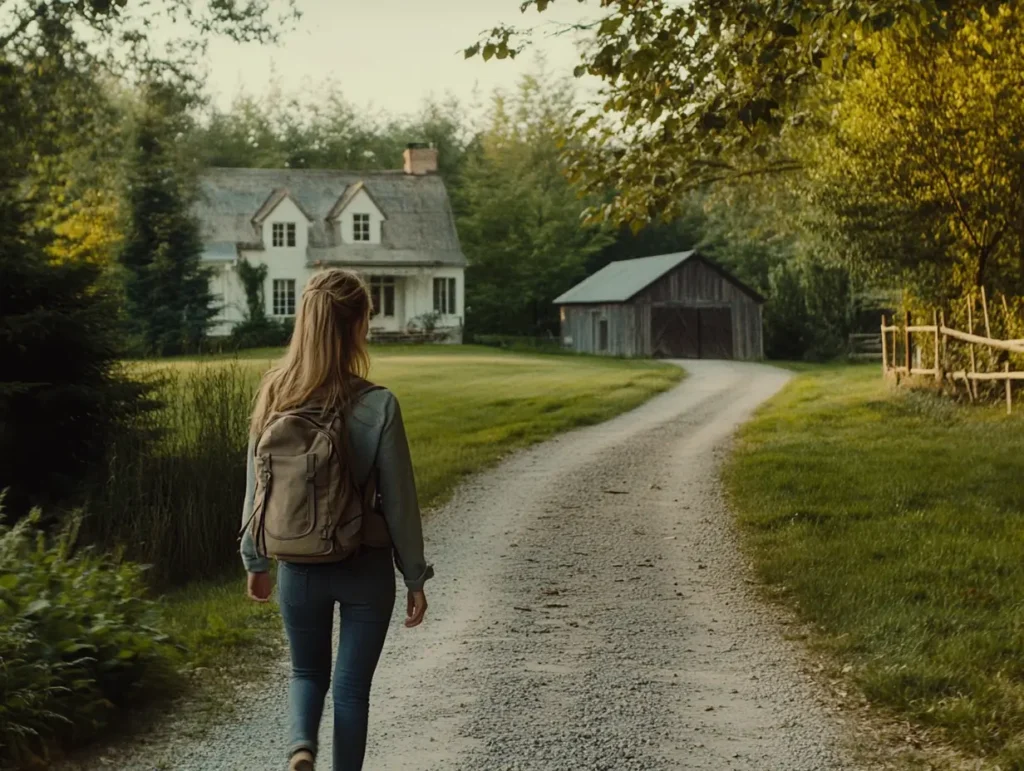
葬儀は数時間前に終わっていた。招待客はぞろぞろと出て行った。残ったのは家族だけだった。納屋はこの日のために息を潜めていたかのように、風化してわずかに傾き、遠くにぽつんと建っていた。クレアは10年以上、この中に入っていなかった。
「サムはグラスを掲げて言った。「衝撃的なことに、まだ走るんだ。新しいスターターが必要かもしれないが、彼女は野獣だ」。「どういたしまして」とクレアがつぶやいた。「どういたしまして」クレアがつぶやいた。「何でもないわ」。彼女は視線を納屋に戻した。
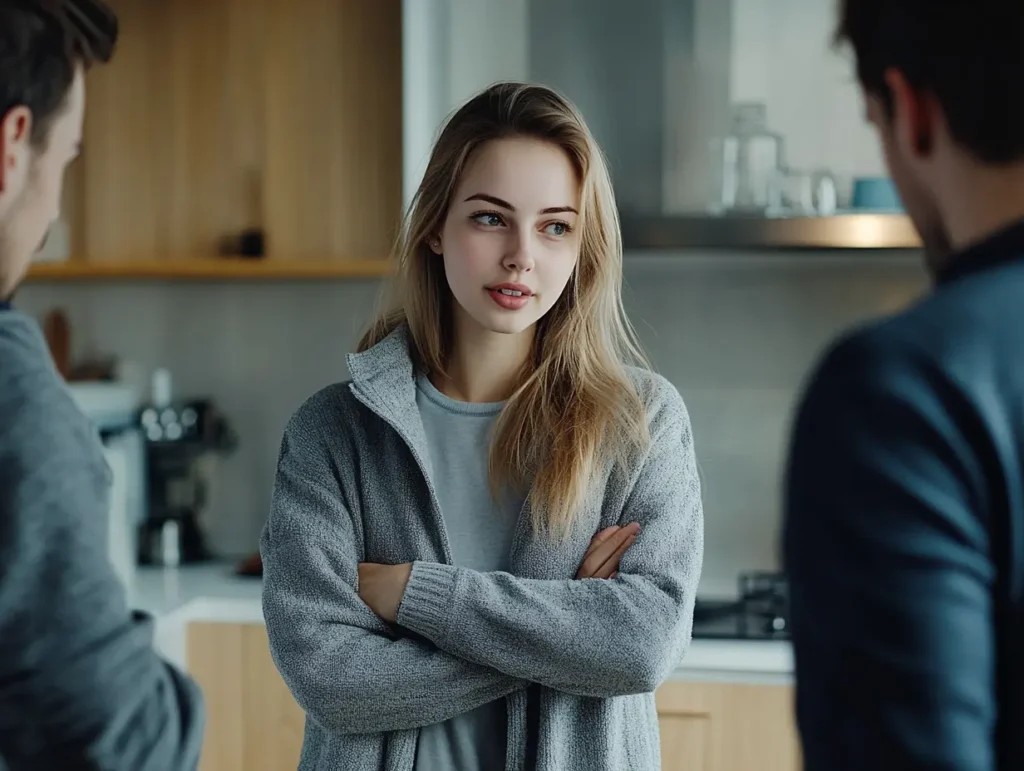
サムはジープと家を手に入れ、ブライアンはボートと家を手に入れた。サムはジープと家を、ブライアンはボートと貯蓄の一部を、クレアは納屋を。クレアは納屋を手に入れた。納屋だけ。誰も反論しなかった。それが公平だったからではなく、彼らにとって理にかなっていたからだ。クレアは金のなる木だった。パパの娘。
パパが溺愛する子。悪いことをしない子だった。だから、彼女が不遇な扱いを受けても、兄たちは誰も気の毒に思わなかった。どちらかといえば、長年の懸案が解決したのだと考えていた。父親が病気になったとき、彼女はすべてを捨ててシカゴでの仕事を辞め、交際も解消し、かつて逃げ出そうと闘った家に戻ってきた。

相続のためではない。罪悪感のためでもない。彼女が戻ってきたのは、父親を愛していたからだ。医師が「数週間か数カ月」と言ったとき、彼女は彼が他人に囲まれて死んでいくのを想像できなかったからだ。あれから14ヶ月。
彼女はすべての薬の名前を覚え、倒れたときに抱き上げる方法を覚え、母親の名前で呼ばれたときになだめる方法を覚えた。彼女はそこにいた。そして今、兄弟たちが遺産相続について冗談を言っているとき、クレアは忘れ去られた本の最後のページのように感じた。
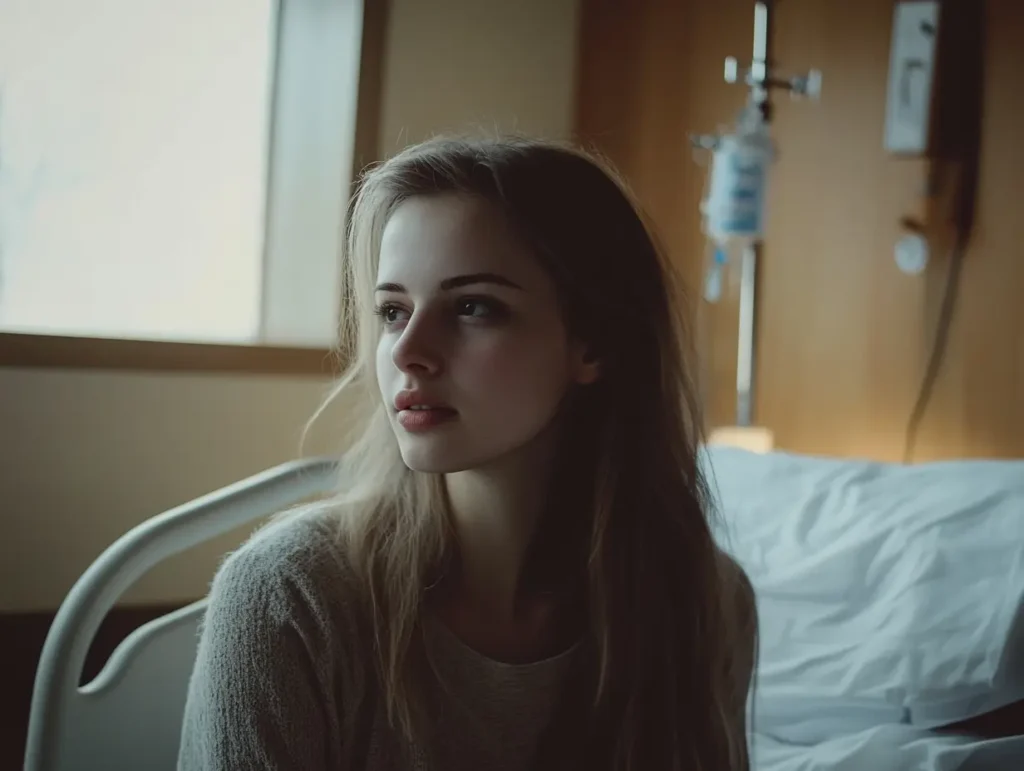
「ブライアンはニヤニヤしながら言った。それって…なんだ?サムは苦笑した。「埃とネズミの巣と、父さんがずっと前に閉じ込めたものでいっぱいだ。実にぴったりだ。父さんはいつも、君にはあの場所との特別な絆があるって言ってた」。
クレアは振り返った。「どういう意味?「覚えてないの?ブライアンは尋ねた。「君が16歳になった後、彼はそこに鍵をかけたんだ。出て行けって。僕らが心配することじゃないって言ったんだ」。「サムは口調を鋭くして言った。”立ち入り禁止 “って言って、今は君のものなんだ」。

ふたりは笑った。しかし、その嘲笑の裏には好奇心がちらついた。一度も。クレアは無理に微笑んだ。「この家を楽しんでね。
彼らがそれ以上言う前に、彼女は歩き出した。彼女が納屋に向かって畑を横切ると、ブーツの下で砂利が砕けた。低い太陽が金色の光をこぼし、埃を金色の斑点のように照らしていた。彼女の父はこの納屋を愛していた。彼女は夜、家に戻る前にざっと見た。

彼女が幼い頃、父は彼女を肩に担ぎ、城を襲撃する騎士になったふりをした。彼は干し草を枕のように積み上げながら、口笛を吹いて働いたものだ。柵の柱の補修の仕方を教え、霜が降りるとポケットに手を入れて暖めた。
しかし彼女が16歳になると、すべてが変わった。納屋は静まり返った。そして彼も、少なくとも彼が内に秘めていたものについてはそうだった。その朝、クレアが納屋に向かうと、二人の兄が腕組みをして横笑いを浮かべながら彼女の後ろをついてきた。

「ついに金庫を開けるのか?とサムが尋ねると、「ただ、父さんが僕たちに隠す価値があると思ったものが何なのかが気になるんだ」とブライアンが付け加えた。クレアは何も答えなかった。重い南京錠があった古い掛け金に手を伸ばした。今はもうなかった。
ドアがギシギシと音を立てて開き、ホコリで濃くなった日差しが一片見えた。3人は中を覗き込んだ。干し草とクモの巣、そして忘れ去られた道具しかない。ブライアンは低く口笛を吹いた。「秘密はもうたくさんだサムは苦笑した。「彼は君のために最高のものを取っておいたようだ」。

二人は振り返り、家のほうへ歩き出した。クレアはしばらくの間、敷居に立ち、擦り切れた木に指をかけた。「私はそれを世話します “と彼女はささやいた。「これがあなたが私に残してくれたものなら……それを大切にする方法を見つけるわ」。
中で影が待っていた。じっと。静かに。そして空っぽではなかった。クレアは深呼吸をして袖をまくり、中に入った。納屋は彼女の記憶よりもひどい状態だった。梁からは色あせたカーテンのようにクモの巣が垂れ下がっていた。道具や棚、横倒しになった錆びた一輪車など、あらゆるものが埃で覆われていた。

ネズミの糞が隅に点在し、窓の一つは内側に砕け散り、ガラスや葉が床に散乱していた。クレアはため息をついた。「わかったわ、お父さん。何を置いていったか見てみよう」。掃き掃除を始めたが、空気が濃くなると肘をついて咳き込んだ。
家畜がいなくなった今、床板のきしむ音が大きくなった。馬房は空っぽで、干し草も目的もなくなって久しい。ベッシー、デューク、ハニーといった使い古された名札が、ひび割れ、色あせながらも門の上に掲げられていた。

彼女はひとつひとつの角に時間をかけた。それが必要だったからではない。しかし、それが懺悔のように感じられたからだ。彼女がここに来るのは何年ぶりだろう。昔は父親の手伝いで馬房の泥を落としたり、ヤギに餌をやったりしていた。
新鮮なわら、甘い飼料、暖かい毛皮。作業中、父はよく口笛を吹いていた。時々、彼女は父と一緒に口笛を吹いていた。2人で調子を合わせたり、外したりしながら。しかし今、静寂が押し寄せている。

彼女は腕が痛くなり、背中が悲鳴を上げるまで何時間も働いた。ようやく外に出ると、ジーンズは埃で汚れており、手袋をはめた手は生乾きだった。空は灰色に染まっていた。夕闇が迫っていた。
サムとブライアンはまだ家にいた。彼女は行くべきでないとわかっていた。彼女はとにかく行った。中に入ると、彼らはキッチンにいて、飲み物を飲みながらブライアンの携帯電話で何かを見て笑っていた。グリルしたステーキとローストガーリックの匂いが、波のように彼女を襲った。

誰も夕食をごちそうしてくれなかった。電話すらなかった。ブライアンはちらりと顔を上げた。「おや、誰かと思えば」。サムは唸った。「クレア、そこに友達はできたか?クレアは引きつった笑顔を見せた。「実は、掃除しているんだ。あのゴミ捨て場を?「あのゴミ捨て場?サムは笑った。”あそこを少しでも良く見せようと頑張ってるんだ” とサムは笑った。ブライアンはグラスを持ち上げた。
「彼女は感謝すべきだ。納屋を独り占めできたんだから」。クレアの胃が締め付けられた。彼女はそれを払いのけようとしたが、声にひびが入った。1年以上も。仕事をあきらめた。私の人生。私は何も求めていない。でも、私が埃や破片以上のものを稼げなかったみたいに言わないで」。ブライアンは肩をすくめた。「金目当てじゃないんだろ?それがどうした?”

サムは身を乗り出した。「見てごらん、何か光るものがあるかもしれないよ」。笑い声がガラスのように擦れた。クレアはそれ以上何も言わずに立ち去った。その夜、クレアは子供の頃の寝室で目を覚まし、天井の扇風機がゆっくりと円を描くように軋むのを見つめた。
彼女の拳は握りしめられていた。胸が熱くなった。相続のせいではない。納屋のせいでもない。彼らが彼女を見ていなかったからだ。翌朝、彼女は納屋に戻り、重い扉を開けた。指は震えていたが、顎は据わっていた。

黙っているのはもう嫌だった。彼女はこの場所で何かを成し遂げようとしていた。クレアは日の出直後、父親の髭剃りの匂いがかすかに残るフランネルにくるまって納屋に戻った。朝は指先を刺すほど冷え込み、納屋の外の背の高い草には、まるで世界が冬を手放すかどうか決めかねているかのように霜がまとわりついていた。
彼女はすぐに仕事に取りかかった。掃き掃除をし、積み重ね、残す価値のあるものを整理した。大したものはなかった。錆びついた道具や壊れたフェンス、革紐がひび割れた鞍などだ。それでも、神聖なものをひとつひとつ修復していくような気分で、この場所に秩序をもたらすのは気持ちのいいものだった。

朝方までに、彼女は最後の干し草の山にたどり着いた。それは納屋の奥の角、古い飼料箱の後ろにあった。彼女が物心ついたときから、その塚はそこにあった。父親が元気で残りを管理できるようになっても、手つかずのままだった。
彼女は逡巡し、埃っぽい薄片に手をかけた。何か…違和感があった。場違い。彼女はため息をつき、干し草を引き離し始めた。見た目よりも重く、塊になっていて、中心部は湿っていた。彼女は手袋を振り払いながら手早く作業し、埃が煙のように舞い上がった。

数分後、彼女の指先が固いものに当たった。彼女は固まった。さらに干し草を脇に払った。木だ。古く、風雨にさらされ、中心には金属のリングがボルトで留められていた。罠の扉だ。心臓が飛び跳ねた。
彼女はしゃがみこみ、縁を触った。それは本物だった。重く、堅く密閉されていた。掛け金はない。リングだけ。彼女は長い間それを見つめ、突然納屋が静かになったことに気づいた。風もない。きしみもない。ただ自分の息と、垂木に巣を作る鳥の柔らかな鳴き声が聞こえるだけ。

どうして彼女はこのことに気づかなかったのだろう。子供の頃でさえ、彼女はこの床を何百回も往復した。馬房の中で鬼ごっこをした。干し草の俵で砦を作った。この一角はいつも…倉庫だった。彼女は金属製のリングに手をかけた。しかし、彼女は手を放した。
まだだ。彼女はゆっくりと立ち上がると、膝についた干し草を払った。明日にしよう。明日開けよう。その夜、彼女は眠らなかった。葬儀の翌日の夜と同じように、彼女はまた天井を見つめた。

あの下に何があったのだろう?なぜ父親はそのことを言わなかったのだろう?ただの倉庫?古い根貯蔵庫?使うことのなかった古い雨よけ?見てごらん、何か光るものが見つかるかもしれないよ」。
クレアは横向きになり、枕を強く握りしめた。納屋はまるで残飯のように彼女に投げつけられた。たぶんそれだけだったのだろう。でも、そうではなかったのかもしれない。翌朝、彼女は懐中電灯と軍手、そして父親の古いこじ開け棒を持って戻ってきた。

彼女が納屋に戻ると、木がうなり、空気が冷え、静寂が深まった。彼女はトラップドアの端に跪いた。指をリングに巻きつけ、引っ張った。そして引っ張った。ひび割れとともに仕掛け扉が開き、何かが何年ぶりかに息を吐き出すような重いうめき声がした。
埃が巻き上がり、クレアは咳き込んだ。蝶番は抵抗し、金属が木に当たって音を立てたが、やがて扉は折れ曲がり、狭い階段が現れた。木製。凸凹。闇に消えていく。クレアは懐中電灯のスイッチを入れ、下を照らした。

ビームは古い階段を照らし、一部は反り返り、一部はひび割れ、10フィートか12フィートほど下の地下室のような場所に続いていた。下から上がってくる空気は、濡れた石やカビのような、古臭く湿った匂いがした。彼女はためらった。しかし、彼女は降りた。
一歩一歩が彼女の体重で軋んだが、踏みとどまった。底で彼女のブーツは土に着地した。壁は粗いコンクリートと木製の羽目板で覆われ、ところどころ古いトタン板で補修されていた。思ったよりも広く、納屋よりも広く、そして寒かった。

彼女は懐中電灯で部屋の中をゆっくりと照らした。部屋は散らかっていた。使い古されたリクライニングチェアが片方の壁に寄りかかり、脚がない。金属製の書類棚が開き、引き出しは空っぽで錆びていた。棚には書類の入った箱、黄ばんだ新聞、ひび割れた写真立てが置かれていた。
隅には古びた冷蔵庫があり、コンセントが抜かれ、ダクトテープで閉じられていた。蜘蛛の巣がカーテンのように垂れ下がっている。しかし、バンカーという感じはしなかった。ストームシェルターでもない。まるで…倉庫のようだった。忘れられた倉庫。普通の。雑然としている無意味。クレアは息を吐き、懐中電灯を下げた。

彼女は突然疲れを感じた。消耗している。これが彼が彼女に残したものなの?壊れた家具やガラクタでいっぱいの、この湿った地下室が?もしかしたらここは、父親が処理したくないものをすべて捨てた場所だったのかもしれない。納屋は贈与ではなく、単なる後付けだったのかもしれない。
彼女はゆっくりと円を描くように振り返り、奥の隅に押し込まれた黒いゴミ袋の山に光を当てた。そのうちの7、8枚は、たるんで互いにもたれかかり、まるで誰も捨てようとしなかったゴミの山のようだった。

彼女は喉が熱くなるのを感じた。あまりにひどかった。父親が衰えていくのを見ながら過ごした数カ月間。兄たちの沈黙。納屋。罠の扉。謎の正体は…これだった。”使える “と彼女は苦々しげにつぶやいた。「その通り。
彼女は近くのゴミ袋に向かい、満足感を得るために、何かをするために、ゴミ袋を破ろうと半分覚悟した。しかし、彼女はそうしなかった。まだ。彼女は懐中電灯を消し、暗闇の中に立って目を慣らした。空気はひんやりと静まり返っていた。頭上では納屋がかすかにきしみ、罠の扉が見えなくなった。

クレアは最後にもう一度部屋を見た。ここには目立ったものは何もなかった。宝もない。秘密のメッセージもない。ただガラクタが高く積まれ、湿っているだけだ。それなのに、何かが彼女の心に引っかかった-不満よりも深い何かが。なぜこれを隠したのか?どうでもいいことなのに、なぜトラップドアで封印したのか?
彼女の手がゴミ袋のひとつに触れた。それは静寂の中で大きな音を立てた。彼女は頭上に納屋の重みを感じ、兄弟たちの笑い声がまだ記憶に新しい。クレアは目を細めた。明日。彼女はバッグをひとつひとつ調べていくだろう。クレアはその夜眠れなかった。

兄たちの目の輝き、ブライアンが彼女をどうでもいいように見送ったこと、誰もいない納屋に響く父の笑い声。彼女は、物事がどのように分割されていたかに平和を作ったと思ったが、今はどうだろう?
今となっては、彼らが彼女を塵に投げ捨て、何かを作れと啖呵を切ったように感じた。だから彼女はそうした。朝までに彼女は納屋に戻り、屋根から落ちたカラスを驚かせるような勢いで仕掛け扉を再び引き開けた。懐中電灯の光が地下室の暗闇を刃物のように切り裂き、ブーツが土に触れた瞬間、彼女はゴミ袋のところへ直行した。

彼女は最初のゴミ袋を掴み、重そうにテープで閉じ、部屋の中央の開けた場所に運び出した。彼女はしばらくゴミ袋を見つめた後、こう言った。彼女はそれを切り裂いた。古着、たたまれたベッドシーツ、傷だらけで車輪のない子供の木製のトラクターのおもちゃのようなものがこぼれ落ちた。
何を探しているのかよくわからないまま、彼女の指はそれらをかき分けていった。一番下に、父親が赤ん坊の彼女を抱いて、二人で干し草にまみれて笑っている、くしゃくしゃになった写真を見つけた。彼女はまばたきをした。移動した。ページがくっついたノート、賞味期限切れの豆の缶詰、6時13分にセットされたままの壊れた壁掛け時計。

そして、埃っぽいが無傷のワインボトルが出てきた。彼女はそれをひっくり返し、苦笑いを浮かべた。1993年のカベルネで、ポストイットが貼ってあった:「思い出に残る一日に。3つ目の袋が彼女に喧嘩を売った。ビニールが伸びて破れそうになったので、彼女はそれを拾い上げ、苛立ちのあまりコンクリートの壁に叩きつけた。
中のボトルは一瞬にして砕け散った。「くそっ!」彼女は叫び、赤ワインがゆっくりと動く傷口のように床一面に広がる中、後ずさりした。そして彼女は聞いた。何かが転がったときの柔らかい金属音。彼女は懐中電灯の光をそこに向けた。

小さな真鍮の鍵が、壊れたリクライニングチェアの土台の近くに落ちていた。クレアはしゃがんでそれを拾い上げた。色あせたリボンでタグが結ばれていた。彼女はそれをひっくり返した。真鍮にC.M.のイニシャルが刻まれていた。
彼女は先ほど壊したゴミ袋を振り返り、それからまだ物陰で待っている他の人たちを見た。彼女の脈は速くなった。恐怖ではなく、より深い何かに引き寄せられたのだ。これはガラクタではない。これは仕掛けられたものだった。クレアは立ち上がり、鍵を強く握りしめた。

彼女の手が震えたのは、寒さのためではなく、不可能な現実が彼女の中に芽生えたからだった。ここには何かがあった。そしてそれが何であれ、父親は彼女にそれを見つけさせたかったのだ。クレアは時間を無駄にしなかった。
最初の鍵を上着のポケットに無事にしまい、彼女は秘密の層をはがすように、残りの袋を追いかけた。埃が舞い、クモの巣が袖にからみつき、こぼれたワインで割れたガラスがブーツの下で砕けた。

バッグを開けると、さらに奇妙なものが出てきた。父親の筆跡で整然と書かれた日記帳など、何十年も前のものである。ひび割れた食器、使いかけの髭剃りセット、カビの生えた新聞紙などだ。
古いアルバムに折り畳まれた子供の頃の絵や、3歳の誕生日にもらった陶器の馬などだ。そして、杉の欠片の強い匂いがする袋の中から、彼女は2つ目の鍵を見つけた。

彼女の父親が日曜日にブレザーのポケットに入れていたのと同じシルクのハンカチで結ばれていた。これは銀色で、最初のものより小さかったが、同じように装飾が施されていた。イニシャルはなかったが、巻かれていたリボンの色は最初のものと同じ深紅で、マルーンに近い色だった。
クレアは踵を返し、手のひらに置かれた2つの鍵を見つめた。「何を言いたいの、パパ」彼女はささやいた。彼女はセラーの残りの部分に振り返った。これは偶然ではないような気がした。彼女の父親はこれを計画した。父が仕組んだのだ。

そして彼女の目は、奥の壁に押しつけられたゴミ袋の曲がった山に止まった。彼女はまだそれに手をつけていなかった。木製のキャビネットが壁に押しつけられ、その後ろに隙間があった。クレアは肩をキャビネットに押しつけ、押した。キャビネットはコンクリートの床を大きくこすり、空洞が見えた。
そこには金庫があった。金庫。古くて鋼鉄製で、埃にまみれていたが、この忘れ物の地下室には紛れもなく場違いだった。壁にはめ込まれ、正面には3つの鍵穴があり、それぞれ微妙に形が違っていた。クレアは膝をついた。

心臓がドキドキした。最初の鍵を一番大きな穴に差し込むと、指が震えた。カチッと音がして鍵は回った。2つ目の鍵を差し込んだ。すると…何もない。2つ落ちた。あと1つ。
彼女は最後の鍵穴を見つめ、不信と期待が入り混じった心臓の鼓動を高鳴らせた。もしこれがそうだとしたら、父親は彼女に何も残さなかったわけではない。彼女にしか見つけられないものを残したのだ。クレアはゆっくりと立ち上がり、残されたバッグを見た。彼女はもう疲れていなかった。怒りもなかった。

彼女は近くにいた。その金庫の中で待っていたものは、単なる遺産ではなかった。メッセージだった。つ目の鍵は簡単には手に入らなかった。彼女が最初に開けた袋は、千切れた雑誌とカビの生えた毛布でいっぱいだった。次の袋には、延長コードに絡まった一対の壊れたランプが入っていた。
クレアは喉の奥で時計のように脈を刻みながら、ひとつひとつをあさった。最後から2番目の袋、歪んだレコードと古いジャケットの山の下で、彼女はそれを見つけた。つ目の鍵。真鍮製の一番小さな鍵で、少し変色しており、同じ深紅のリボンで結ばれていた。

クレアは揺らめく地下室の光にそれをかざし、その瞬間の重みが肩にのしかかるのを感じた。彼女の指は、金庫に戻りながら、その鍵にしっかりと巻きついた。最初の鍵はまた簡単に回った。2つ目も。そして3つ目が来た。カチッ。
深い機械音が地下室に心臓の鼓動のように響いた。クレアは本能的に後ずさりした。ドアがギシギシと音を立てて開くと、金庫の上部からホコリが舞い上がった。彼女は手を伸ばした。最初は空っぽだと思った。

そして、父親のサインリングのかすかな刻印が入った蝋で封をされた封筒を見た。その下には、きれいに積み重ねられた紙幣、金貨、古い宝石類、そして持ち上げるとジャラジャラと音を立てるビロードのポーチがひとつ。パスポート、古い証書、銀行の元帳がその奥に収められていた。
しかし、クレアはまだそんなことは気にしていなかった。彼女は封筒を開けた。中には黄ばんだ厚紙に手書きの手紙が入っていた。彼女の父親が書いたもので、しっかりとした斜めの文字だった:「カップケーキ、これを読んでいるということは、諦めていなかったということだ。

「あなたは決してあきらめなかった、子供のころから。私はいつもあなたのそういうところが好きだった。納屋を捨てたのは、価値がないと思ったからじゃない。私たちのものだったから。あなたなら埃や腐敗を乗り越えて見てくれると思ったから。覚えていてくれると思ったから
“そして、最後の冒険を一緒にしてほしかったから。ここにあるものはすべて君のものだ。あなたが稼いだからじゃない。あなたが残ってくれたから。私を最後まで見届けてくれた人。このことを最も理解してくれると信じていた人。あなたはいつも私の野性的な人だった。私の好奇心。私の心。愛しています、お父さん”

クレアは手紙を胸に押し当てた。すぐに泣くことはなかった。壊れた思い出と新たに見つけた宝物に囲まれた地下室の静寂の中で、彼女はただ長い間そこに座っていた。
彼女は震える息の中で、そっと、静かに微笑んだ。彼は忘れていなかった。彼はずっと彼女のことを見ていたのだ。クレアは慌てて兄たちに知らせようとはしなかった。金の延べ棒を振りかざしたり、トロフィーのように手紙を振りかざしたりして家に押し入ったりはしなかった。

彼女はただ静かに地下室に鍵をかけ、日が暮れるまで納屋を掃除し、手に埃をつけ、胸に軽いものを抱えてその場を去った。その夜、彼女は誰もいない農家のキッチンテーブルに座り、父の手紙を冷めた紅茶の入ったマグカップの横に置いた。
彼女はそれをもう一度読み返し、静寂の中で言葉を口にした。彼は知っていた。彼は知っていた。彼らが見ようとしなかったものを。そして今、彼女も知っている。翌朝、ブライアンが “納屋暮らし “についてまた悪口を言ったとき、クレアはひるまなかった。彼女はそれに抵抗しなかった。ただ彼を見て微笑んだ。
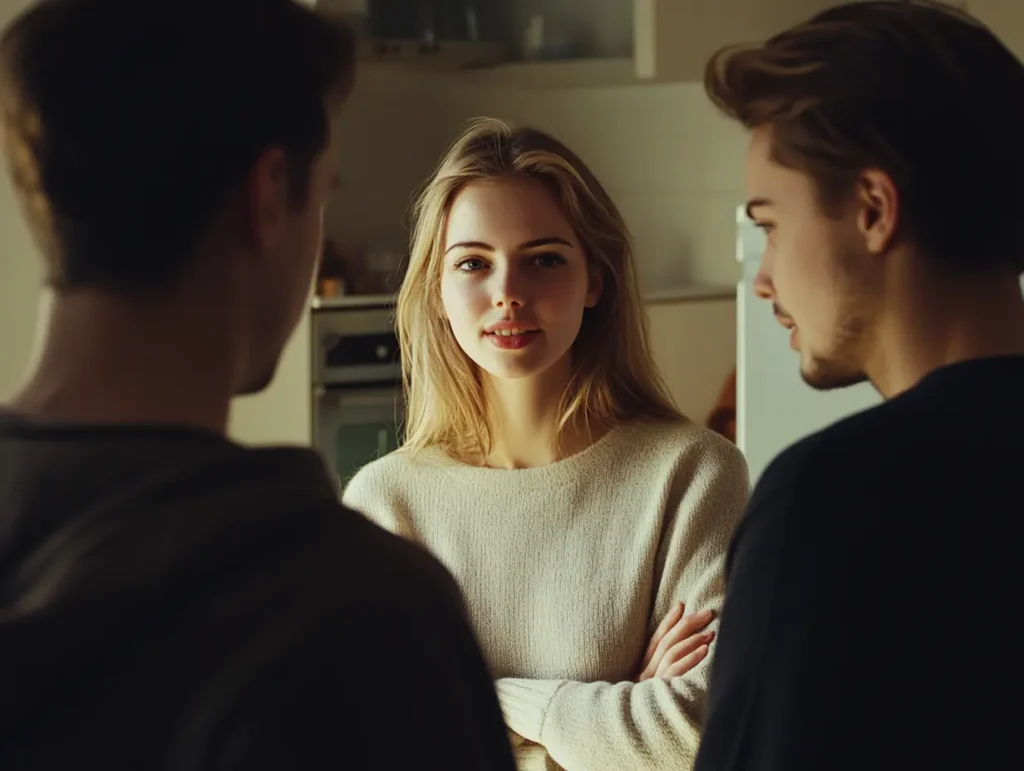
自惚れてもいない。苦笑いでもない。穏やかに。彼女はもう何かを証明する必要はなかった。代わりに彼女は納屋に戻り、今度は掃除ではなく、再建に取りかかった。窓を開けた。埃を払ってきれいに積み上げた。
庭から花を持ってきて、空のメイソンジャーに生けた。少しずつ、この場所は家でも記念碑でもなく、隠れ家へと変わっていった。彼女のだ。それから数週間後、遺言が解決し、言い争いが一段落した後、クレアは町で物静かな不動産屋に会った。

彼女は地元の慈善団体や小さな農場、そして前年にすべてを失ったこの先の家族のリストを彼に渡した。納屋の裏の空き地に花とハーブの庭を作るためだ。
残りは父親の名義で贈与した。サムとブライアンは知らなかった。その必要はなかった。彼らは欲しいものを手に入れた。彼女もそうだった。ある日の午後遅く、彼女はフェンスに咲く野草の最初の列に水をやりながら、父のことを思い出した。

そして数ヶ月ぶりに、父のことを思い出しても胸が痛むことはなかった。彼女は微笑んだ。「パパ、見つけたよ」彼女は手のひらについた土を払いながらささやいた。「今までありがとう風が強くなった。太陽が木々の陰に隠れた。葉の静かなざわめきの中で、彼女はパパの口笛が聞こえそうになった。
